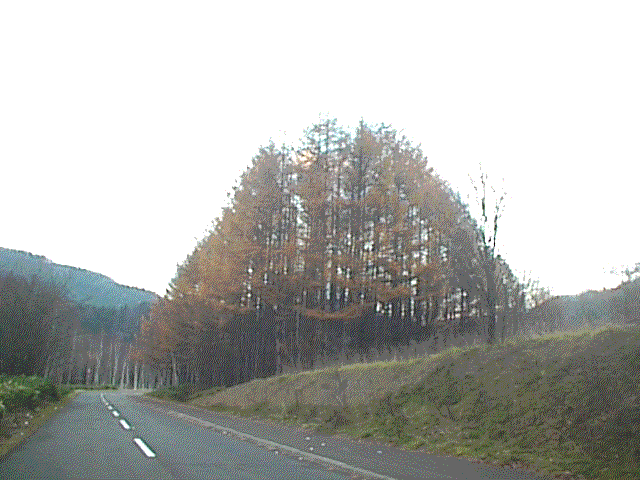
1998年度 初任者研修共通研修第5日
表計算ソフトコース
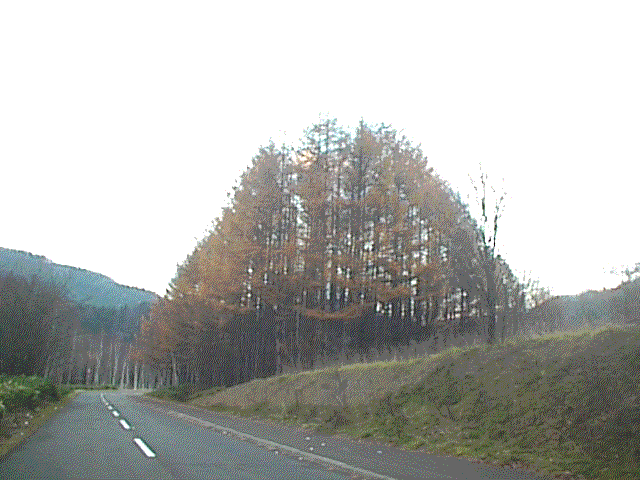
平成10年9月24日(木) 会場:札幌市立八条中学校
はじめに
学習指導要領の改訂に関し、小,中,高等学校段階を通じてコンピュータ等を積極的に活用すると明記されてている。中学校では,技術・家庭科の「情報とコンピュータ」を必修とし,発展的内容については生徒の興味・関心等に応じて選択的に履修するとなっている。コンピュータの整備についても平成12年度以降の整備計画ではコンピュータ教室に加え,普通教室,学校図書館等にも配置し,校内をネットワーク化、校務の情報化を進めるために保健室,進路指導室,職員室等にも設置とあり、学校現場のネットワーク化が今後急速に進展することが予測される。インターネットへの接続に関しては、平成13年度までにすべての中学校に導入される計画があり、学校と外部の接続という大きな環境の変化が起こることとなります。
大変革の時期を前にして今以上に使う機会が増えるコンピュータを、今日の研修では興味を持ってこれから自己研修をつんでいこうという気持ちの きっかけづくりができればといいなと思います。
今日の流れ
まずは肩がこらないよう進めたいと思います(コンピュータ嫌いを増やしたくない)
コンピュータになれた人、触ったことのない人等いろいろな方がいると思いますが。みんなで慣れていこうということで、初心者の方を想定して講座を進めていきます。わからないところはそのままにせず、どんどん質問していって下さい。表計算以外の活動が多いですがマウスと日本語が使えないとできないので、他のことも前向きにやりましょう。
1、話 教員になって思うこと(民間とちがうなとかんじること)
一生が勉強ですね その他
2、基本操作 起動終了 窓のあやつりかた、マウスの操作、
3、マウスに慣れよう1インターネットエクスプローラを使いイントラネットに触れる
バーチャル教科書、生徒作品紹介、アダムスくんの紹介、web指導案の紹介その他
4、日本語入力に慣れよう 日本語入力と保存、呼び出し練習
一太郎で簡単な文章を入力し、HTML形式にします。
5、マウスに慣れよう2DOGAを使って作品作りクリックドラックの感触をつかむ
6、自己紹介 DOGAで作った作品を交流しながら、自己紹介をしてもらいます。
7、みんなの作品評価、web上で作品を評価してもらいます。ここで集めたデータは後ほど表計算ソフトで加工します。
1〜7 までで、さあ表計算ソフトを使おうという準備ができました。
8、表計算ソフトの基礎
9、表計算ソフトの応用
10、まとめの話
起動から印刷まで
ウィンドウズ95になりいろいろなアプリケーションで操作の統一が図られています。今回のコンピュータ実技講座を受けることにより、ハイパーキューブや一太郎のみならず他のアプリケーションにも応用がききます。まずは、ウインドウズ95の世界に慣れてみましょう。
基本1、起動しましょう。(まずはここから)
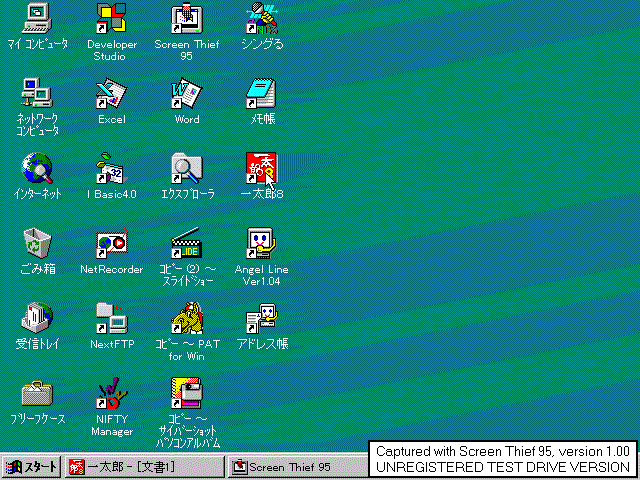 上はウィンドウズの基本画面です。一太郎のアイコンをダブルクリックしてみましょう。
上はウィンドウズの基本画面です。一太郎のアイコンをダブルクリックしてみましょう。
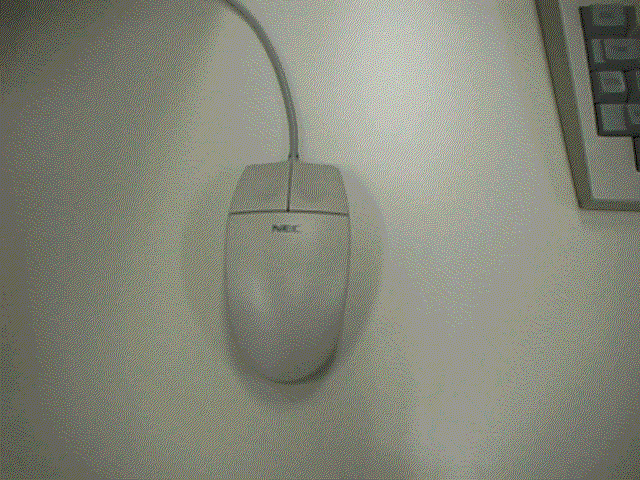 windowsの基本操作
windowsの基本操作
クリック:マウスの左ボタンを1回押しすぐ離す操作
ダブルクリック:マウスの左ボタンを2回すばやく押す動作(よくここでつまづく人がいます、リズム良く押しましょう)
ドラック:マウスの左ボタンを押しながら動かす操作
右クリック:関連するメニューを出すとき
マウスの操作はとにかく慣れることです。慣れることによりコンピュータを感覚的に操作することができます。今日の講座でもたくさん慣れることになります。
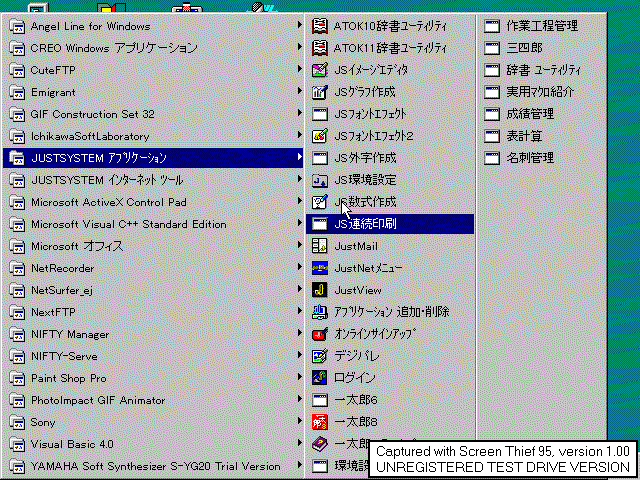 一太郎の起動に関してはアイコンをクリックする以外にスタートボタンのメニューから選ぶこともできます。
一太郎の起動に関してはアイコンをクリックする以外にスタートボタンのメニューから選ぶこともできます。
スタートボタンからプログラムを選び一太郎のアイコンをクリックすることにより起動します。この操作をすることにより使用するコンピュータで使える道具(アプリケーションソフト)がわかります。
例題1
まず 一太郎を起動しましょう。
起動しましたね、では入力する前にウインドウの操作に慣れてみましょう。
演習1−1 起動した一太郎の窓の大きさをいろいろ変えてみましょう

右上にボタンが並んでいますね。右端の×はアプリケーションの終了ボタン
真ん中のボタンはウインドウの大きさを変化させるボタン
左の_はウインドウの最小化ボタンです
自由に大きさを変えれますか?
※窓の場所を変えたいときは上のバーをドラックして離します。
演習1−2
さあ窓の操作できますね。もうなれてきた人は、ディスクトップのアイコンからインターネットエクスプローラをダブルクリックし起動して見やすい大きさにしてから、八条中ホームページを探索してみましょう。エクスプローラで八条中ホームページを見るためには多くのクリックが必要です。たくさん操作して慣れてみましょう。
見るところ:
・バーチャル教科書、現在試作中のweb上の教科書です。常に最新のデータ内容でさらにこの教科書が実用化すれば改訂があっという間にできます。
・web指導案、今後の指導案作成の一つの形でwebを利用することにより、学校内、地域内のみならず、他県の先生とも指導案を練りながら作成することができます。
・アダムスくん HTBのインターネット放送です。有害情報がふくまれておらず、生活に密着した最新情報を得ることができます。
・作品ページ 生徒の表現などで良いところを吸収してみましょう。
・コンピュータ部のページ 余裕があれば見てみましょう。少し専門的です。
マウスに慣れたところでDOGAを使って簡単な作品を作ってみましょう。この作品はこのあと全員発表会を行います。
1,第三角法のアイコンでDOGAのパーツアセンブラが起動します
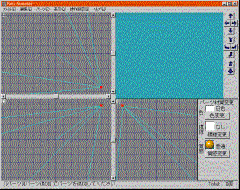
左が起動画面です。これは第三角法(覚えているでしょうか?初めて見る人もいますね)の画面と同じです。赤い点はカメラの位置を表しています。たいていの操作は、クリックとドラックでできます。どんどんマウスのボタンを押していくといつのまにかすばらしい作品が生まれると思います。
2、まずはまっさらな画面にパーツをおきましょう。
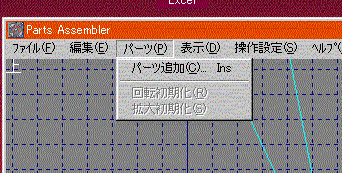
バーチャル教科書にもパーツ一覧があるので参考にしてまずはイメージをふくらませましょう。感覚的に使えると思うのでどんどん触ってみて下さい。
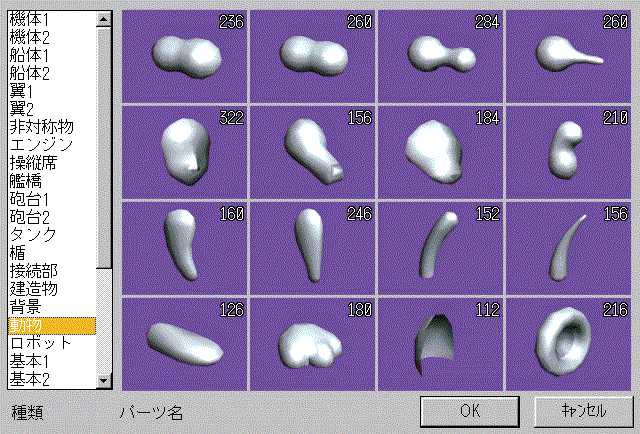
メニューのパーツからパーツ追加を選びます。
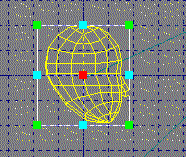
パーツをおくとすぐイメージが表示されます。
ドラック(マウスの左ボタンを押しながら動かすこと)で部品を操作します。
赤い点は場所の移動、緑の点は回転、青い点は大きさが変わります。
3、パーツをおいたら、材質、色を決めましょう。
必要に応じてカメラ位置も変えるといいです。
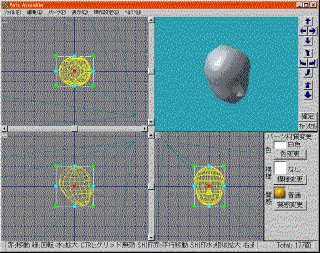
クリックすれば変更されます。
4、パーツをどんどん組み合わせて配置や大きさ角度を工夫しましよう。
5、左右対称の部品は、編集の左右対称複写してみましょう。
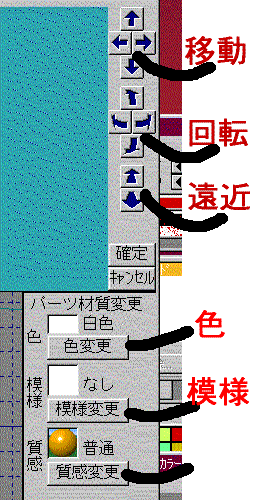
発表会では最後にインターネットエクスプローラを使い評価をしあいます。しっかりと発表しあいましょう。
マウスにも慣れましたね。次はキーボードに慣れましょう。
基本2、日本語を入力してみましょう
1 ローマ字入力とかな入力の切り替え方
キーボードの 「かな」 キーを押すことでローマ字入力とかな入力が切り替わ ります
※ローマ字入力とかな入力どちらがよいかよく聞かれますが、その人の好きな方法でというのが答となります。また、初めてキーに触れる人には、キーを覚える数が少なくてすむのでローマ字入力をすすめています。
2 上書きと挿入の状態を切り替える
画面の左下に 挿入 と表示されていますが。 「INS」 キーを押すことに切り 替わります。普段は挿入モードにしておくことをすすめます。
3 ひらがな、かたかなを入力する
次の図の様に あ を左クリックするとメニューバーが現れます。全角カタカナをクリックする事により以後の入力がカタカナに固定されます。
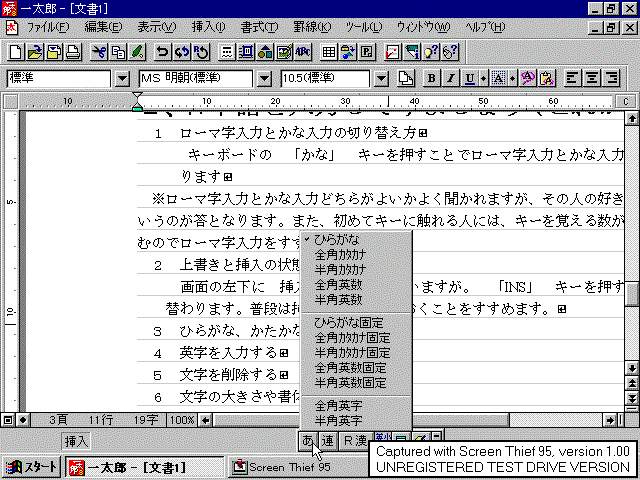 また、文字を入力後 f・7 キーを押すとひらがなからカタカナに変えられます
また、文字を入力後 f・7 キーを押すとひらがなからカタカナに変えられます
4 英字を入力する
文字を入力語 f・9 キーを押すことにより英字に変わります
f・8 キーを押すことにより半角英字に変わります
XFER キーを 押すと連続して半角英字を入力できます。
5 文字を削除する
書いた字を消すときは
カーソルの一つ前を消すとき BS キーを使います。
カーソルの場所を消すとき DEL キーを使います。
6 文字の大きさや書体を変える
※ ドラッグを覚えましょう。 マウスの左ボタンを押しながら左右に動かすと範囲を選択できます
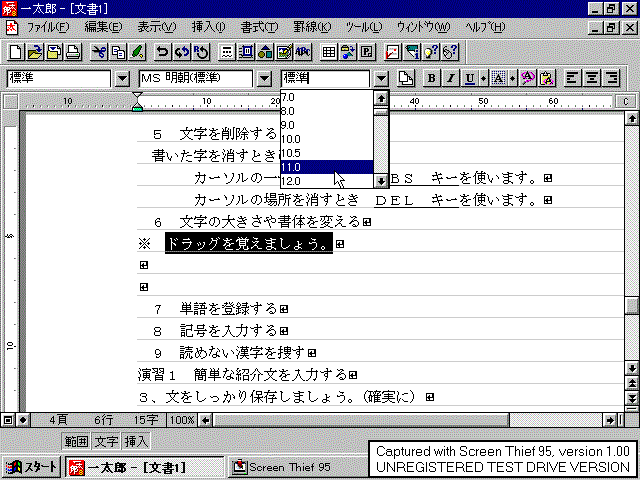
※ポイントとは時の大きさを表しこの数字が大きいほど字も大きくなります。
選択した部分の文字の大きさを変えるには上図の様に文字バーをクリックします。同様にフォントも変更できます。
これから、実際に操作しながら、クリック、ドラック、キーボード入力に慣れましょう。
演習2
自分の好きな入力方法で、(初めての方はローマ字入力?)あ〜ん、A〜Z、自分の名前を入力してみましょう。その後、フォントを変えたり大きさを変えたりしてみましょう。
7 単語を登録する
メニューバーの ツール 単語登録を選択することによりよく使う言葉を登録できます。
演習3
自分の名前と、学校名を簡単に変換できるよう登録してみましょう。
例えば1と入力し変換すると自分の名前、2と入力し変換すると学校名など
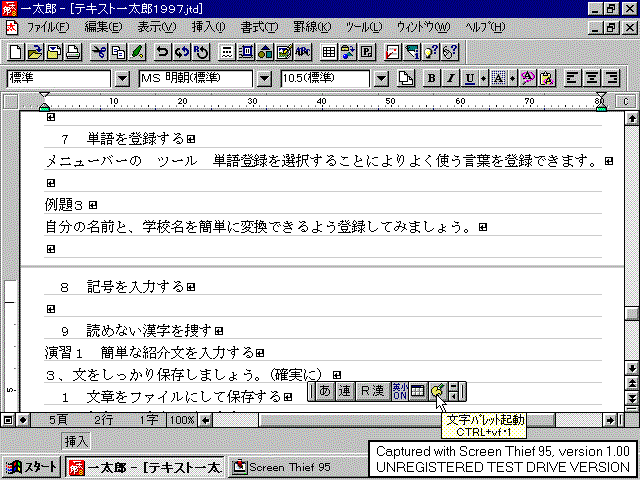 8 記号を入力する
8 記号を入力する
左図の様に文字パレットをクリックすると
下図のような文字パレットが起動し記号を入力できます。
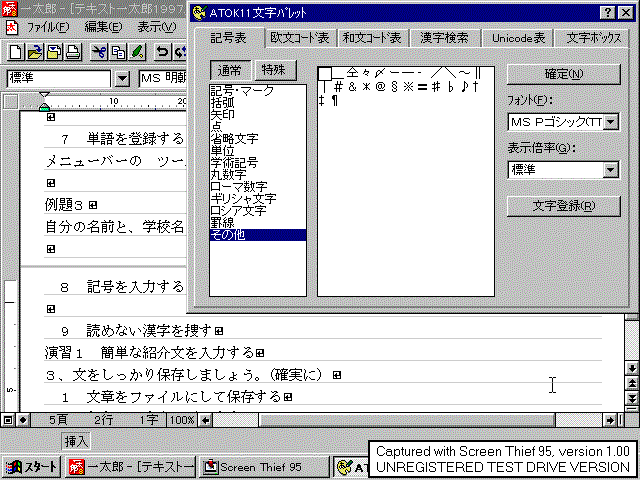
9 読めない漢字を捜す
文字パレットの漢字検索を実行すると読めない漢字を部首で探すことができます。
基本3、文をしっかり保存しましょう。(確実に)
どんなソフトでも使うときにまず確かめて欲しいのが、データの保存法です。これがしっかりできればコンピュータを使えますと胸をはれます。
1 文章をファイルにして保存する
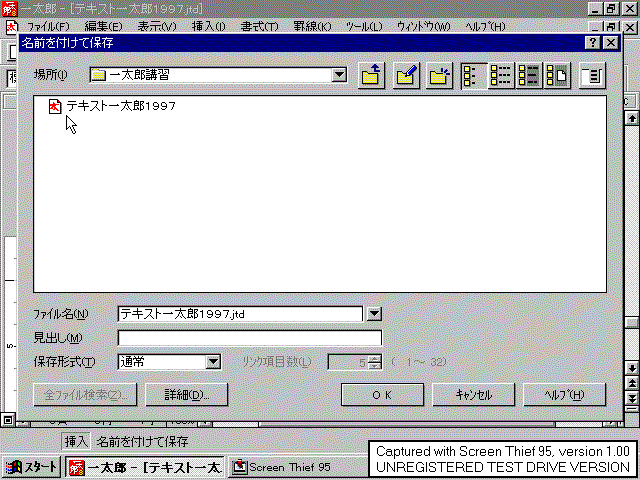
メニューバーの ファイル 名前をつけて保存 をクリックすると上図のような画面になります。ファイル名は255文字までです。okをクリックすると保存されます。
2 保存した文章を呼び出す メニューバーから ファイル 開く
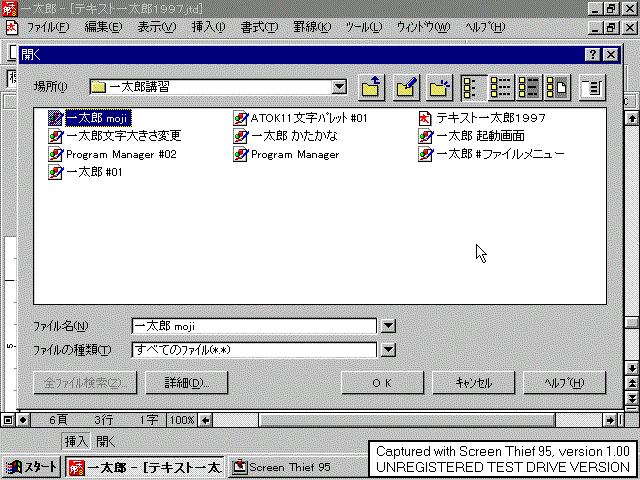
呼び出したいファイル名をクリックすると呼び出されます
保存と呼び出しはどんなアプリケーションでも基本的なことです。確実にできるようにしておきましょう。
例題4 今の文章を好きな名前を付けて保存し、それを呼び出してみましょう。
例題5 簡単な自己紹介文をWEBにのせる
1、自分の一太郎文章を出しておく
2、ファイルメニューのHTML形式で保存を選ぶ
3、保存場所は Yドライブ − sken
ファイル名は 今使っている台の番号 (例 15)
全角で(大きな数字)
4、OKする
これで保存されます。結果は八条webで確認してみましょう。
みなさん、基本操作にだいぶ慣れたことと思います。
表計算ソフトを体験してみましょう。
さあ、どんどん使ってみましょう
1、 はじめに
コンピュータの上達のためにはどんどん、使うことが大切です。使ってみることによりソフトウェアの活用のイメージが湧きさらなる応用につながっていくはずです。現在のウインドウズ環境ではエクセル、ロータス、三四郎といろいろな表計算ソフトがありますが、どれも基本的な表作りの考え方は何も変わるところはありません、逆に言えばどれか一つを覚えれば他も使えるはずです、これを機にこれからの活用へのイメージをふくらませてもらえたらと思い。バラエティに富んだ例題を用意しました。全部できる必要はありません、あなたにとってこれからの仕事や生活への応用のヒントが少しでもつかめたらと思います。
まずは、今回使うキューブカルクに慣れてみましょう。
キューブとは・・・・・バーチャル教科書で基本操作の解説
2、例題に取り掛かる前に
それぞれの例題は、基本的なもので、あなたの想像力しだいでいろいろな応用が聞くと思います。
表計算ソフトというと計算という名から固苦しいイメージを持ちがちですが、この表計算ソフトは使い方によって成績処理から競馬の予想までいろいろ応用がききます。できれば基本的な例題を解きながら、自分の仕事や、生活に応用するとしたら…・という考えがあればこの会も有意義なものになることと思います。
3、さあ初めてみましょう。
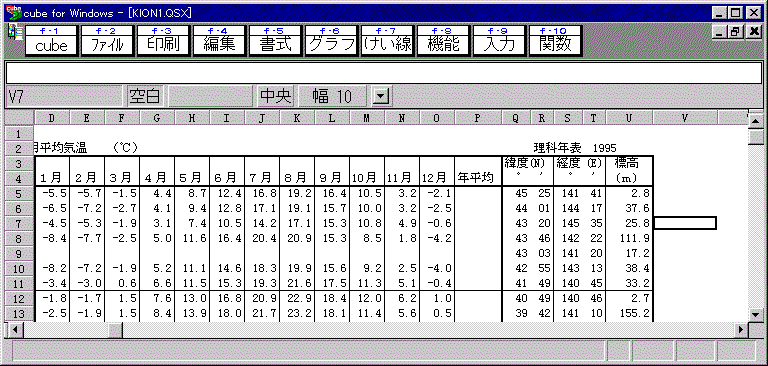 上の図は表計算ソフトの基本画面です、表計算ソフトは セルという 縦方向の列、横方向の行で表される升目を基本としています。上図ではV7のセルが 囲まれていますがこの現在編集可能なセルを カレントセル といいます。
上の図は表計算ソフトの基本画面です、表計算ソフトは セルという 縦方向の列、横方向の行で表される升目を基本としています。上図ではV7のセルが 囲まれていますがこの現在編集可能なセルを カレントセル といいます。
表計算演習1
まずは上図のような既存の表を読み出してみましょう。
データディスクから、JAPANというファイルを読みだし、平均気温に適合する数式を入れて合計欄の下に日本の気温の最大値、最小値のセルを作ってみましょう。余裕があれば、あなたなりの工夫をどんどんしてみてください。
ヒント
1、数式の入れ方 まずは年平均の稚内のセルに合わせて −
f.10の関数をクリックします。− 関数のリストから 平均をクリックしokします。
− 稚内の1月から12月までをドラックし − リターンキーを押します。
2、コピーの仕方
ふつうは、一カ所コピーし、コピーされる領域を選択しペースト(貼付)しますが、このソフトでは 編集 の 連続複写 で下方向へコピーします。
表計算演習2
表計算のイメージをつかもう
さあ、関数を使ってこの資料を加工してみましょう。みましょう。またグラフにもチャレンジしてみましょう
表計算演習3 セル幅を調節してみましょう
データディスクから BYOUIN というファイルを読み出し、この表を使いやすく並べ替えてセル幅を調節し、罫線なども見やすくつけてみましょう。
セル幅は
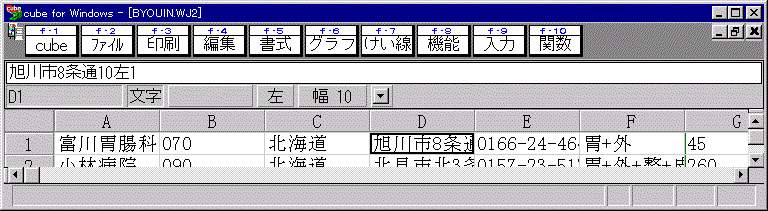 セルの一番上のアルファベットの部分を動かしカーソルの形が変わったときドラッグすると変化します。
セルの一番上のアルファベットの部分を動かしカーソルの形が変わったときドラッグすると変化します。
罫線は、線を使い分けると見栄えのある表になります。
表計算演習4 慣れましょう
データーディスクより KANSU というファイルを読みだし 式をいれグラフをひょうじしてみましょう。
他の関数式のセルも作ってみましょう。
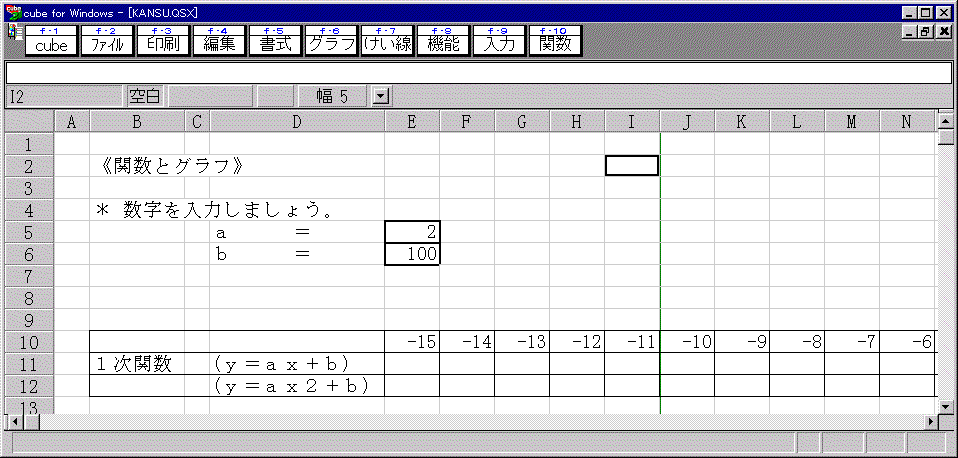
ヒント ここでは絶対座標と相対座標の考え方が必要です。$a$1のように$をつけたセルを絶対座標といい、コピーしても指し示す位置は変化しません。 TABで設定
表計算演習5
データディスクより KONDATE というファイルを読みだし、合計値を作り食品群別のレーダーチャートを作り、印刷してみましょう
表計算演習6
データディスクより 不完全な家計簿 を読み込み自分に合った表に変えてみましょう。このデータはあくまで参考例です。
表計算演習7
他の表計算ソフトも基本は同じだということを体験してみましょう。ロータス123を起動して表を作って見ましょう。もしくはハイパーキューブの表を読み込んでみましょう。
ヒント! ハイパーキューブで保存するときにロータスでわかる形式で保存しましょう。
表計算演習8
最後に
だいぶ疲れたと思いますが、それと同時に慣れて来たことと思います。いろいろな課題をこなしていくうちに、コンピュータを何かに使ってみようというイメージを持っていただけたら幸いです。